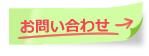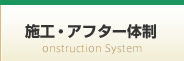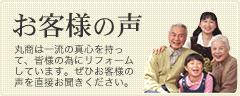政府は、医療費が高額になった患者の自己負担を一定額に抑える
「高額療養費制度」の上限額の引き上げ幅に関し、
7~16%を軸として調整に入った。
上限額は1カ月当たりで世帯ごとに設けられ、現在8万円程度の場合、
単純計算で約6千~1万3千円増える。
2025年度から開始する。
医療費の膨張を抑え、現役世代を中心とした保険料の負担を
軽減するのが狙い。
関係者が14日、明らかにした。
上限額は年収によって異なる。
住民税非課税など所得が平均より低い人向けには、
引き上げ幅を小さくすることも検討する。
26年度には年収区分を細分化し、高所得者はより高い上限額とする見込み。
今後、詳細を詰める。
現在の上限は、年収約370万~770万円の場合は8万円程度。
7~16%引き上げると、8万6千~9万3千円程度となる。
上限額が17万円程度となる年収約770万~1160万円の場合、
約1万2千~2万7千円増えて18万2千~19万7千円程度となる。
アメリカのトランプ次期大統領は、実業家のイーロン・マスク氏を政府の支出を
見直すために新設される「政府効率化省」のトップに任命すると発表しました。
トランプ氏は12日、イーロン・マスク氏と共和党の候補者レースに出馬していた
実業家のビベック・ラマスワミ氏の2人が共同で新たに設ける
「政府効率化省」を率いると発表しました。
トランプ氏は「官僚機構を解体し、過剰な規制を撤廃し、無駄な支出を削減し、
連邦政府機関を再編する道を切り開いてくれるだろう」としています。
マスク氏はアメリカの連邦予算のおよそ3割にあたる「2兆ドルを削減できる」
と発言していて、
声明では「政府の無駄遣いに関与している多くの人々に衝撃を与えるだろう!」
と強調しました。
また、トランプ氏は国防長官に、保守系のテレビ「FOXニュース」で
司会者を務める退役軍人のピート・ヘグセス氏を起用する方針を明らかにしました。
声明によりますと、ヘグセス氏は陸軍の兵士として、
イラクやアフガニスタンに派遣された経験があるということです。
さらに、駐イスラエル大使にはイスラエルを強く支持する
元アーカンソー州知事のハッカビー氏を指名すると表明しました。
ハッカビー氏は牧師で、イスラエルによるヨルダン川西岸の入植に賛成しているほか、
イスラム組織「ハマス」に対しては強硬な姿勢を取るべきだと主張しています。
このほか、CIA=中央情報局の長官には、第一次政権の国家情報長官だった自らの側近、
ジョン・ラトクリフ氏を充てる方針も発表し、人事を加速させています。
国立社会保障・人口問題研究所は12日、
2050年までの都道府県別世帯数の将来推計を発表した。
全世帯に占める1人暮らしの割合は全都道府県で上昇し、
50年には東京都の54・1%を最高に半数以上の27都道府県で40%を超える。
65歳以上の1人暮らし世帯の割合も増え、高知や徳島など32道府県で20%を超える。
若者が都市部に集中し、高齢化や未婚化、少子化で家族を構成する人数が
少なくなっていることが要因だ。
推計は5年ごとで、20年の国勢調査を基に実施した。
全国の世帯総数は20年の5571万世帯が50年には5・6%減の5261万世帯となり
40道府県で20年を下回る。
中でも、秋田県の29・1%減を筆頭に、青森、岩手、山形、長崎、高知、徳島など
9県で20%超減少する。
一方、1人暮らし世帯は20年の2115万世帯が50年には2330万世帯に増える。
増加するのは32都府県で、特に沖縄、埼玉、滋賀、千葉の4県は増加率が20%を超える。
全体に占める1人暮らし世帯の割合の全国平均は44・3%で、
東京、大阪、京都、福岡、北海道、神奈川、鹿児島の各都道府県が45%超。
また、1世帯あたりの人数が40年には半数以上の都道府県で2人を下回る。
20年時点で2人以下なのは東京だけだが、40年に26都道府県、50年には34都道府県になる。
最も少ないのは東京、北海道の1・78人で、多いのは山形の2・15人。
高齢化を背景に、1人暮らしのうち65歳以上の高齢者の世帯は全ての都道府県で増加し、
20年の738万世帯が50年には1084万世帯(46・9%増)になる。
全体に占める割合は13・2%が20・6%まで上昇。
32道府県で20%を超え、高知(27%)、徳島(25・3%)、愛媛(24・9%)
などが特に高くなる。
家族のいる人も含めた高齢世帯(世帯主が65歳以上の世帯)も増え、
全体に占める割合は50年には21県が50%を、東京を除いたすべての道府県が40%を超える。
75歳以上の1人暮らしも全都道府県で増加。
沖縄、滋賀、埼玉、茨城各県では20年から50年で2倍以上になる。
2024年10月度の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、
件数が909件(前年同月比14.6%増)、
負債総額は2,529億1,300万円(同17.8%減)だった。
件数は、2カ月連続で前年同月を上回り、7月以来、3カ月ぶりに900件を超えた。
10月に900件を超えたのは2013年の959件以来、11年ぶり。
負債総額は、3カ月連続で前年同月を下回った。
2024年では7月の7,812億600万円に次ぐ2番目の高水準となった。
負債100億円以上は2件(前年同月6件)と減少したが、
同5億円以上10億円未満20件(同25.0%増)、
同1億円以上5億円未満168件(同0.5%増)と中堅規模で増加した。
また、同1億円未満は701件(同19.4%増)で、
構成比は今年最高の77.1%と8割近くを占め、
小・零細規模の倒産を主体に推移した。
集計対象外の負債1,000万円未満の倒産は、48件(前年同月47件)発生した。
1-10月の累計は8,323件(前年同期比17.6%増)で、
11年ぶりに年間1万件超えが現実味を帯びてきた。
四半期別では、2024年1-3月2,319件(前年同期1,956件)、
4-6月2,612件(同2,086件)、7-9月2,483件(同2,238件)と
夏場に一服したものの高水準で推移し、2022年4-6月期から
10四半期連続で前年同期を上回っている。
資金需要が活発になる年末を控えるが、
コロナ禍の資金繰り支援で生じた過剰債務を解消できない企業は多い。
現状は業績不振の企業の息切れに加え、売上増に伴う資金調達が追いつかない
企業の黒字倒産が押し上げる形で、倒産は増勢をたどる可能性が高い。
10月、東京・三鷹市で起きた強盗未遂事件で、新たに実行役とみられる2人の男が逮捕されました。
名古屋市の職業不詳・荒木颯斗容疑者(28)と、
住所・職業不詳の渡辺創容疑者(24)は10月、
仲間と共謀し三鷹市大沢の住宅に侵入し、住人の70代の男性の首を絞めるなど
して金品を奪おうとした強盗未遂などの疑いがもたれています。
警視庁によりますと、荒木容疑者と渡辺容疑者は実行役とみられいずれも
闇バイトに応募し、指示役から指示を受けて犯行に及んだとみられています。
警視庁は2人の認否を明らかにしていません。
この事件を巡っては、実行役3人が住宅に押し入ったと見られていて、
これまでに京都市に住む大学生の佐圓昌紀容疑者(23)が逮捕されいています。
四国電力によりますと、9日夜、四国4県で一斉に停電が発生しました。
四国電力送配電は、9日深夜にホームページでリリースを出し、
今回の停電の原因を「周波数低下リレー」だと発表しました。
映像は停電発生時の高知龍馬空港です。一斉に照明が消えています。
四国電力送配電によりますと20時22分に最大36万5300戸の停電が発生し、
21時49分に解消しました。
午後8時半時点で発生していた停電は以下の通りです。
香川…6万2500戸
愛媛…11万1900戸
徳島…11万1400戸
高知…7万9500戸
【香川県で発生していた停電】(午後9時時点)
東かがわ市…4300戸
【高知県】(午後9時時点)
南国市…11300戸
宿毛市…13100戸
土佐清水市…9800戸
四万十市…23000戸
香南市…6100戸
香美市…7100戸
吾川郡いの町…50戸
幡多郡三原村…1200戸
幡多郡黒潮町…3800戸
【愛媛県】(午後9時時点)
松山市…約12,300戸
今治市…10戸未満
宇和島市…約900戸
八幡浜市…10戸未満
新居浜市…約100戸
西条市…約35,700戸
大洲市…約3,700戸
伊予市…約1,300戸
東温市…10戸未満
北宇和郡 松野町…約2,200戸
北宇和郡 鬼北町…約3,700戸
南宇和郡 愛南町…約300戸
停電は徐々に解消していて、午後10時までには復旧しました。
停電が発生した直後の、高知県西部・土佐清水市では、
まち全体が暗闇に包まれ、「車のヘッドライトの明かりが頼り」という状況になりました。
また、同じく高知県西部の四万十市中村では、一部の地域でおよそ40分間ほど停電しました。
中村警察署では、停電の直後から、警察官が交差点に立って車を誘導したり、
パトカーで停電を呼びかけたりしたということです。
警察によりますと、高知県内では、これまでに被害の情報は入っていないということです。
四国電力送配電は、9日の深夜にホームページでリリースを出し、
今回の停電の原因を「周波数低下リレー」が動作したことだと発表しました。
米大統領選で減税や積極財政を訴えたトランプ氏が返り咲いたことを受け、
金融市場はリスクを積極的に取る姿勢が強まり、
円安・株高の「トランプ相場」となった。
ただ、「米国第一」を唱えるトランプ氏が関税強化などを実行に移せば、
世界経済は不透明感が強まり、市場の先行きは読みにくくなる。
市場では投票日の11月5日より前から、
金利高、ドル高、株高が同時に起きる「トランプ・トレード」が進行。
米経済の堅調さもあり、10月初めに3・7%台だった米国10年債利回りは
足元で4・4%台まで上昇。ドル円相場は約1カ月で10円以上、円安・ドル高が進んでいた。
関税強化や不法移民対策、1期目に実現した「トランプ減税」の恒久化は
いずれも物価上昇(インフレ)を引き起こしやすい。
財政出動で経済が過熱すれば、米連邦準備制度理事会(FRB)の
利下げペースは緩やかになると見込まれ、長期金利が上昇。
金利の高いドル資産が買われた。
投開票でトランプ氏の優勢をいち早く織り込んだのは6日の東京市場だった。
日経平均株価(225種)は一時1100円超の上昇を見せ、
円相場は1ドル=154円台まで円安が進んだ。
その後のニューヨーク株式市場ではダウ工業株30種平均が急伸。
約3週間ぶりに史上最高値を更新した。
大手証券アナリストは「今年最大のイベントを通過し、市場の不透明感が晴れた。
様子見姿勢だった投資家が動き出した」と指摘し、年内の株価は底堅く推移するとみる。
トランプ氏率いる共和党は4年ぶりに上院で多数派を奪還したが、
下院選は接戦となっている。
ホワイトハウスに加え、共和党が上下両院の多数を握る「トリプルレッド」となれば、
大統領の政策が実現しやすくなる。
三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは
「来年1月の就任早々に景気刺激策を打ってくるとの思惑が強まれば、
(年内に)1ドル=155~160円まで円安が進む可能性がある」と指摘する。
だが、トランプ相場がいつまで続くかは見通せない。
トランプ氏は外国製品には10~20%、
中国製品には60%の関税を一律に課す方針を示している。
米国の貿易赤字解消に向けドル安を志向するとの見方もあり、
ドル高の是正に動く可能性もある。
国際経済に詳しい東京女子大の長谷川克之教授は
「米中対立が激化すれば、グローバル化が一段と揺らぐ。
保護貿易の拡大や世界経済の分断は大きなリスク要因だ」と指摘。
「景気浮揚効果という短期的なプラスより、
中期的なマイナスの方が大きいのではないか」との見方を示す。
NTTの島田明社長は7日の記者会見で、トランプ氏の経済政策について
「影響を見極めていきたい」と警戒感をにじませた。
市場関係者の間でも「株価にプラスかマイナスか分からない」との見方が少なくない。
建設会社幹部は「円安による資材価格の高騰が懸念材料」と語った。
トランプ政権の閣僚人事や通貨・財政の基本姿勢が確認できないと、
経済の先行きを見通すのは難しく、株や為替相場は当面、
トランプ氏の言動に左右される展開が続きそうだ。
ロシア政府は、米大統領選でのトランプ氏勝利宣言を受け、
ウクライナ戦争の終結に向けた過去の発言がどう反映されるかを
様子見する姿勢を示した。
大統領府のペスコフ報道官は、トランプ氏は選挙期間中、
ウクライナ戦争を終わらせたいという重要な発言をしていたが、
それが行動につながるかは時間が経てばわかると指摘。
米国は非友好的な国で、ウクライナ戦争に
「直接・間接的に関与していることを忘れてはならない」と述べた。
またプーチン大統領がトランプ氏勝利を祝福するかわからないとし、
米国との関係は歴史的な低水準にあるとの見解を示した。
その上で「米国は外交政策の軌道を変えることができる。
(大統領就任後の)1月以降にわかるだろう」と語った。
ロシア外務省は、米国には超党派で反ロシア的だとし、
トランプ氏について幻想を抱いていないとの見解を示した。
政府系ファンドであるロシア直接投資基金(RDIF)のキリル・ドミトリエフ総裁は、
トランプ氏の勝利は関係修復のチャンスとなる可能性を指摘した。
同総裁は元ゴールドマン・サックスのバンカーで、過去にトランプ陣営と接触したことがある。
ロシア前大統領のメドベージェフ安全保障会議副議長は、
軍事的に米国を最大の後ろ盾とするウクライナにとっておそらく悪いニュースだとし、
「トランプがどれだけ戦争に出費するかが問題だ」と述べた。
先月、神奈川県横浜市の民家で発生した強盗殺人事件で
「回収役」として逮捕された女が夫を通じて指示役とつながったと
みられることが新たにわかりました。
夫は特殊詐欺に関与したとして先月北海道警に逮捕されていて、
警察は背景にある組織の全容解明を急いでいます。
この事件は、10月16日、横浜市青葉区の民家で住人の後藤寛治さん(75)が
暴行を加えられ死亡した状態で見つかり、現金約20万円が奪われたものです。
この事件をめぐっては、「実行役」の1人として宝田真月容疑者(22)が
逮捕されているほか、
奪われた現金の一部を都内の公園で回収した「回収役」として
11月2日、木本未穂容疑者(30)が逮捕されています。
未穂容疑者はこれまでの調べに対し、容疑を認めていますが、
その後の捜査関係者への取材で「夫から何度もお願いされて引き受けた」
と供述していて、夫を通じ「指示役」とつながっていたとみられることが
新たにわかりました。
一方、未穂容疑者の夫の木本康寛容疑者(31)は、
北海道札幌市内で発生した特殊詐欺事件に関わったとして
10月19日、北海道警に逮捕されていて、
警察は背景にある組織の全容解明を急いでいます。
東京・葛飾区の住宅で男性が縛られた状態で見つかった強盗事件では
逮捕された男が、10時間ほどこの家にとどまり金品を物色していたことが分かりました。
自称・山内裕太容疑者(29)は2日、仲間と共に葛飾区の住宅で
住人の男性の顔を殴ってけがをさせたうえ、
粘着テープで縛って現金などを奪った疑いが持たれています。
その後の捜査関係者への取材で、山内容疑者が10時間ほどこの家にとどまり、
金品を物色するなどしていたことが分かりました。
山内容疑者は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されましたが、
「近所の人が来たからもう逃げられないと思い、警察官が来るまで待った」
と供述しているということです。
現場からは他に複数人が逃げていて、警視庁が行方を追っています。