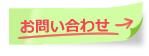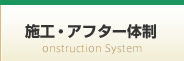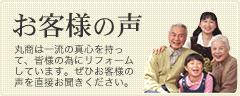2025年4月12日、米国とイランはオマーンの首都マスカットで、イランの核開発問題を巡る協議を行いました。
この会合は、2018年に米国が核合意(JCPOA)から離脱して以来、両国間で初めての公式な対話の場となりました。
協議はオマーンの仲介により間接的な形式で行われ、両国は「建設的な雰囲気と相互の敬意の下で」核開発と制裁解除について話し合いました。
イラン外務省のアラグチ外相と米国のウィトコフ中東担当特使は、会合後に短時間、対面での会話も交わしました。
ホワイトハウスは声明で、協議は「非常に前向きで建設的」だったが、課題は「非常に複雑」だと指摘しました。
両国は協議を継続することで合意し、次回の会合は4月19日にローマで開催される予定です。
今回の協議は、長年にわたる米イラン間の対立を解消するための新たな取り組みとして注目されています。
今後の交渉の進展が、中東地域の安定化や国際社会の安全保障に大きな影響を与える可能性があります。
出典:「イランと米国、協議継続で合意-核開発巡る公式会合は『建設的』」「米イラン、『核問題協議は建設的』 来週再開で合意」
トランプ米大統領は9日、世界各国を対象に発動したばかりの相互関税の一部を90日間、
一時停止すると発表しました。同時に中国への関税を145%としました。
中国の対抗姿勢の背景や関税による経済への影響などについて、
防衛研究所の飯田将史理論研究部長に聞きました。
トランプ政権の高関税政策に対し、中国は一時、「最後まで付き合う」と表明するなど、
徹底して対抗する方針を示してきました。
中国が強気な姿勢をとる背景には大きく二つの事情があったと思います。
中国は9日までの段階では、「トランプ氏は全世界を敵に回して貿易戦争を繰り広げている。
グローバルサウス諸国や先進国も巻き込んでいるので、各国と連携すれば米国を追い込める。
しばらく、がまんすれば米国が妥協する」と考えていたようです。
もう一つは、国内的要素です。中国経済は停滞しています。中国軍の人事を巡る不満もあるようです。
一般市民や軍、中国共産党の中に習近平(シーチンピン)国家主席体制への不満や
反感が広まりつつあると思います。
習政権として、ナショナリズムをあおって求心力を回復したい思惑があったのでしょう。
しかし、主なターゲットを中国に絞ったトランプ氏の9日の発言で、
最初の事情が大きく変わりました。
中国ははしごを外された状況で相当焦っていると思います。
中国内からは、トランプ氏が最初からこうした構図を狙っていたのではないかと
疑う声も出るかもしれません。
昨年1年間に自宅で亡くなった一人暮らしの人は全国で7万6020人で、
このうち、死後8日以上経過して見つかった人は2万1856人に上った。
警察庁が11日、初めて年間を通じての統計を発表した。
「孤独死・孤立死」の実態把握を進めてきた内閣府の作業部会は同日、
最終報告を取りまとめ、「孤立死」者数を把握するための目安として、
死後8日以上経って見つかったケースを扱うことが適当と指摘。
このケースは生前に社会的に孤立していたことが強く推認されるとした。
警察庁によると、昨年に警察が取り扱った死者20万4184人のうち一人暮らしで
自宅で亡くなった人は4割近くの7万6020人だった。
年代別では、65歳以上の高齢者が5万8044人で、8割近くを占めた。
10代でも62人、20代でも780人いた。
死亡してから数日以内に発見される人が目立ち、4割近くが当日か翌日に発見され、
7割超は1週間以内に見つかっていた。
一方で、死後8日以上経過して発見された2万1856人のうち、1カ月以上は6945人、
1年以上は253人いた。死後8日以上経過したケースでは、男性が8割を占めた。
10日の米ニューヨーク株式市場で、主要企業で作るダウ工業株平均が前日終値より
1014.79ドル(2.50%)下落し、3万9593.66ドルで取引を終えた。
前日はトランプ米政権による相互関税の一部の一時停止で、史上最大の上げ幅を記録したが、
インフレ(物価高)や景気後退への懸念は根強く、下げ幅が2100ドルを超える場面もあった。
米大企業を幅広く網羅するS&P500指数は3.46%、ハイテク株中心のナスダック総合指数は
4.31%と主要3指数がそろって反落した。
ナイキ(8.29%)、半導体大手のエヌビディア(5.91%)などが大きく下落した。
トランプ政権は9日、相互関税の一部を一時停止した一方で、
中国からの輸入品に対しては125%に引き上げた。中国側も84%の追加関税を発動するとしており、
米中間の関税を巡る応酬は激化している。
さらに、10日には米CNBCなどが、ホワイトハウスが「125%」としていた中国への累計の追加関税率について、
これまでに発動済みの追加関税と合わせて「145%」になると回答したと報じた。
インフレや景気減速への不安が高まり、一気に下げ幅が拡大した。
取引開始前に米労働省が発表した3月の消費者物価指数は、インフレの鈍化を示す結果だった。
しかし、これまでに発動された関税政策の影響が今後出るため、鈍化は一時的との見立てもあり、
懸念はぬぐえなかった。
米トゥルーイスト・アドバイザリー・サービシーズのマイク・スコーデレス氏は、
相互関税の一部が一時停止されても、これまでより税率が高い状況に変わりはないと指摘。
「(9日からの)大きな揺れは、株価が底を打つサインではなく、
これからも変動が続くというサインだ」と話した。
ロシアのプーチン大統領は19日、トランプ米大統領が意欲を示す
両国の首脳会談に前向きな姿勢を示した。
前日にサウジアラビアで行われた米ロ外相会談を高く評価し、
「ドナルドに会いたい」とトランプ氏をファーストネームで呼んだ。
ただ、「結果が出るよう準備する必要がある」とも述べ、
会談には制裁緩和など米側の歩み寄りが必要との考えを示唆した。
訪問先のロシア北西部サンクトペテルブルクで報道陣の取材に答えた。
プーチン氏は「ウクライナ危機も含め、ロシアと米国の信頼関係を高めないと
解決は不可能だ」と強調。
中東や宇宙など様々なテーマが米ロの議論になるとし、
特にエネルギー分野での協力が重要だと指摘した。
「ドナルドと久しぶりに会いたい。親密な関係ではないが、
彼が(前回の)大統領だったときは両国の関係について議論した」と述べたが、
「お茶やコーヒーを飲み、将来を話すために会うのは不十分だ」とし、
会談には何らかの成果が必要だとの考えを示した。
米国のルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相らは18日、サウジアラビアで会談。
ロシア側は、北極圏でのエネルギー開発などを話したとしており、
米国に対ロシア制裁の緩和を求めたとみられる。
アメリカのトランプ大統領が日本時間の2月19日朝、
引き上げを目指す自動車関税の税率について「25%程度だ」と表明しました。
専門家にトランプ大統領の発言の影響について聞きました。
アメリカ トランプ大統領:
「4月2日に話すことになるが、自動車への関税は25%程度になるだろう」
トランプ大統領は関税を適用する対象国については言及せず、
4月2日にも詳細を説明すると話しました。現在、日本の乗用車に対する関税は2.5%で、
日本が対象国となれば10倍になります。
この発言に市場は敏感に反応しました。
トランプ関税への警戒感から自動車関連株を中心に売られ日経平均株価は下落。
2月19日の終値は18日より105円79銭円安い、3万9164円61銭円でした。
アメリカの25%程度の関税の引き上げが、愛知の自動車産業にもたらす影響について、
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの塚田裕昭さんに話を聞きました。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 塚田裕昭さん:
「25%が実現すると、自動車産業の比重が大きい東海地方にとっては大きなマイナスになる」
一方で、25%程度と表明したことには別の狙いがあるといいます。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 塚田裕昭さん:
「トランプさんの狙いは輸出ではなく『(自動車を)アメリカでつくれ』。
アメリカでつくれば雇用も生まれてアメリカにとっていい。
実際には何の交渉もなしに『25%関税で決まり』という話にはならないのではないか」
ただ、25%より低い税率となっても、日本にとっては厳しい状況が続くと見ています。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 塚田裕昭さん:
「関税はそこまで上げません。アメリカへの投資を増やして
アメリカでの(自動車)生産の割合を高めてくれ、という条件で妥結すると、
輸出への影響は小さくなるが、徐々にアメリカでの(自動車生産の)比重が増えて
国内の生産が減る。日本の空洞化につながり、日本経済にとっては望ましくない」
「年収103万円の壁」の見直しを巡って自民・公明の与党と国民民主党との協議が再開し、
自民党は最大で160万円に引き上げる案を示しました。
約2カ月ぶりに再開された年収103万円の壁の見直しの協議で、
自民党は所得税の基礎控除に特例を設け年収200万円までの人は160万円に
引き上げる案を提示しました。
年収200万円から500万円までの人については133万円に引き上げるとしています。
これに対し、国民民主党は「所得で分けるべきではない」と反発しました。
きょう発表された日本のGDP=国内総生産は、去年1年間で0.1%のプラスとなり、
4年連続のプラス成長でした。
ただ、私たちの根強い「節約意識」が、もう一段の経済成長をはばんでいることも
浮き彫りとなっています。
都内に住む高島さん一家。夫婦共働きで、4歳になる子どもと3人で暮らしています。
支出の一つ一つを家計簿アプリで記録していて、
前の年より食費と光熱費が月1万円以上増加したといいます。
とりわけ打撃となったのが…
「昔は5キロの価格で2000円ぐらいだったが、今同じ値段だと2キロしか買えない」
「野菜がもう50円(値上がり)とか400円とかになってるんだよなー」
「キャベツ400円なっていたね」
コメや野菜の高値が続くなか、献立の工夫で節約をしています。
「味変で前の日に作った鍋に味噌を溶いて味噌汁にしたり、
2日同じ味にならないけど新しく買ってくるより(安い)」
きょう発表された去年1年間のGDPでも「個人消費」の弱さが浮き彫りとなりました。
GDPは好調なインバウンドなどを背景に、4年連続でプラス成長となった一方、
およそ6割を占める「個人消費」はマイナス0.1%と、コロナ禍以来初めて、
4年ぶりにマイナスに転じました。
食品の相次ぐ値上がりを背景に、支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」も
28.3%と、1981年以来、43年ぶりの高水準に。
「先に値上げが来て、それを自分側の賃上げで少し火消ししてるような感覚で受けてます」
高島さんが勤める会社では去年、7%ほどの賃上げがあったといいますが、
物価高の前には「焼け石に水」だといいます。
今後、私たちの財布のひもは、緩むのでしょうか。
第一生命経済研究所 シニアエグゼクティブエコノミスト 新家義貴氏
「賃金に関していうと、今交渉している春闘は高い伸びになりそう。
ただ、物価が予想以上に高どまっているのが下押しになるので、
実質的な賃金はほとんど増えないんじゃないかな」
高い賃上げが期待できる一方、4月にかけては7000品目以上の“値上げラッシュの春”が。
日本経済の浮揚に必要な、物価高を超えて賃金が上がる好循環には、
まだ時間がかかりそうです。
パウダースノーを武器に、世界的リゾートに成長した北海道のニセコ地域。
投資熱は冷めず、円安を追い風にインバウンド(訪日外国人)の流入も止まらない。
食品スーパーには、外国人向けの1折3万円を超える生ウニが並び、飛ぶように売れている。
バブルのような好景気に沸く一方で、労働力が枯渇し、
時給水準が東京より高い2000円を超えるまでに高騰している。
人を集められず、閉鎖する介護事業所も出てきた。
外国人の交通事故も一冬500件を超し、住民とのトラブルも増えている。
拡大を続けるニセコの現状に迫った。
ここは本当に食品スーパーなのか――。
ニセコ地域の一角、倶知安町の「マックスバリュ倶知安店」には、
世界的なリゾート地にふさわしい高級食材が並んでいた。
「外国人客が多い冬期間は観光客に満足してもらう商品を豊富に取り揃えている。
やはり味にこだわらないと需要はない」(店長の田村誠さん)
北海道産生ウニが1折で3万2184円。
急速冷凍したタラバガニのボイルには2万7864円の値札がついていた。
霜降りの和牛もきれいに陳列されている。
地元住民が目を丸くするような金額だ。
店内を見わたすと6割が外国人。高級食材をためらいなく、買い物かごに放る。
アメリカの男性は「どの商品もアメリカより安いし、この品質なら全然高くない。
せっかく日本に来ているから、おいしいものを食べないとね」と満面の笑み。
かごをのぞくと総額11万5000円の食材が入っていた。
「私には縁がないかな。品ぞろえが良く安く買えるので、ほっとしている」。
地元住民の買い物客はうらやましそうに外国人を見つめていた。
ニセコ地域は倶知安、ニセコ、蘭越の3町を指す。
2023年度の外国人宿泊数は、統計の残る2006年以降最多の延べ73万8800人。
12月から3月のハイシーズンは関係者の間で「ニセコ100日戦争」とも言われている。
スキー場のふもとにあり、最もにぎわう倶知安町の「ひらふ坂」は目の前には
雄大な羊蹄山が広がる絶好のロケーション。1戸10億円を超えるコンドミニアムや別荘、
高級ホテルが並ぶ。
1平方メートルで70万円以上する土地もあり、価格は10年前の倍。
札幌の高級住宅地よりも高いところがあり、投資熱は一向に冷めない。
配偶者や恋人からのドメスティックバイオレンス(DV)に苦しみ、
警察に被害を相談する男性が近年急増している。
全国の都道府県警では、令和5年に過去最多となる2万4684件の相談を受理。
女性からの相談の半数以下にとどまるものの5年前の約1・5倍、
約20年前の170倍に増えた。
「男は強くなければならない」「女性からの暴力や暴言にも耐えるべきだ」。
DV被害者の支援団体では、こうした社会の風潮に変化が生じ、
隠れた被害が顕在化したためとみる。
■「男のくせに」
「稼ぎが少ないクズ野郎」「お前はATMだ」
横浜市内のNPO法人「女性・人権支援センター ステップ」理事長の栗原加代美さんのもとには、
DV被害に悩む男性が多く訪れる。
栗原さんが相談を受けた関東地方に住む40代男性は、妻から日常的に暴言を浴びせられ、
毎晩のように性行為を強要された。行為を拒むと裸で寝ることを強いられたという。
「男のくせに」。妻の口癖が日中、自宅を離れていても頭をよぎるようになり、鬱病を発症。
仕事が手につかなくなって退職を余儀なくされた。
夫からの暴力に耐えかねた妻が相談窓口へと駆け込む-。
DVに付きまといがちなイメージの通り、10年ほど前は相談者のほぼ全員が女性で男性はまれだった。
現在では、数百人に及ぶ毎月の相談者のうち20~30人が男性だといい、
栗原さんは「男性の人数は年々増えている」と明かす。
■夫婦で殴り合いも
警察庁のデータによると、パートナーからDV被害を受けたとの相談件数は、
令和5年は8万8619件で、男性からの相談はうち27・9%となる2万4684件。
いずれも過去最多だった。
相談体制の整備や被害者保護などを目的とした「配偶者暴力防止法」が平成13年に施行。
翌14年の男性からの相談は142件に過ぎず、およそ20年で170倍超にまで膨らんだ計算になる。
DV問題に携わる警察幹部は「昔は女性ばかりが被害者だったが、今は夫婦で殴り合ったり、
男性が一方的に暴力を振るわれたりする例もある。
丁寧に話を聞かなければ構図が判然としないことも多い」と語る。