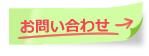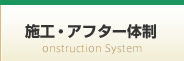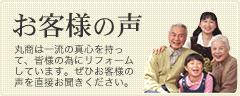精神科の訪問看護事業者で最大手とされる「ファーストナース」(東京)が、
患者の症状や必要度に関係なく、可能な限り訪問回数を制度の上限である
週3回にするよう全社的に看護師らに指示していたことが
5日、分かった。
共同通信の取材に約10人の現・元社員が「3回は必要ない患者も多い」などと証言、
過剰な診療報酬の請求に当たる可能性がある。
社内のLINE(ライン)メッセージや内部資料も入手した。
同社はここ数年で急成長し、「あやめ」という名称で
東北から中国地方まで18都県で約240カ所の訪問看護ステーションを運営。
利用者は主に精神障害者で、1万人前後いるとみられる。
診療報酬の過剰な請求は架空請求などの不正とは異なるが、
報酬は税金や保険料で賄われているため、国民負担が必要以上に増えることになる。
専門家は「事実であれば不適切だ」としている。
同社は取材に対し,
「症状などに鑑み、利用者に訪問回数の増加を提案することはあるが、
(社員に)一律に指示することはない」と答えた。
~工事について~
刈谷市のお客様宅、電気配線工事
を紹介します。
<工事内容>
既設分電盤 解体・撤去
既設幹線 撤去
既設外電気配線 撤去
既設1階電気配線 撤去
<電気配線交換工事>
分電盤交換工事
幹線交換工事
外電気配線交換工事
1階電気配線交換工事
施工前

施工中





施工後



今回の契約は
電気配線が傷み、
劣化してるので、
配線・分電盤を取替える事で、
安定した状態になるように
施工に当たりました。
今後もお客様の暮らしにあった、
工事提案、施工に当たります。
政府・日本銀行による「為替介入」の観測が広がり、
外国為替市場の対ドルの円相場が乱高下している。
しかし、円安・ドル高の基調に変わりはない。
海外での稼ぎが多い企業や、インバウンド(訪日客)の誘客にとって
円安は追い風となる一方で、
原材料やエネルギーで輸入依存度の高い中小企業の経営を直撃する。
中小企業は製造工程の見直しや調達先の変更などの工夫で乗り切る構えだが
対策にも限界がある。コスト増分の価格転嫁も進んでいない。
「原材料の大幅な値上げが年間に幾度もあり、製造業は苦しめられている」。
素材メーカーの山本化学工業(大阪市)の山本富造社長は円安進行による窮状を語った。
外国為替市場では、日米の金融政策の違いを主因とする円安ドル高が続いている。
円安になれば商社や自動車などの大企業は海外事業の円建て収益の増加などで恩恵を受ける。
一方、原材料などの輸入物価が上昇するため、
小売りなど内需中心の中小企業はコスト負担が増加することになる。
円安の影響に関して、日本商工会議所の小林健会頭も4月17日の記者会見で
「大企業と中小企業で正反対。大企業は海外資産があって、
(海外収益を見込める)輸出もできる。
中小企業は輸出比率が小さいし原材料高をもろにかぶる」と発言。
中小企業は円安による負の影響が大きいとの見方を示した。
中小企業が円安を克服するにはコスト上昇分の価格転嫁がカギを握るが、
東京商工リサーチが近畿2府4県で2月に行った調査では、
企業規模を問わず「価格転嫁が全くできていない」としたのは
276社中92社(33・3%)。
コスト上昇分の半額以下の転嫁率にとどまったのは192社(69・5%)に上った。
では、中小企業が取れる対策はないのか。パナソニックホールディングス副社長で
関西経済同友会代表幹事の宮部義幸氏は4月30日の会見で
「取引先が海外なら、そこに対して競争力のあるビジネスはできないか。
材料費や人件費の上昇分を転嫁し、高付加価値のものを提供することに尽きる」と話した。
大企業の中には供給網を見直し、国内回帰を進めるなど円安対策を講じるケースもある。
大阪府内の食品製造メーカーの中小も
「輸入原料の調達先の変更や国産品の割合を高めることも検討する」とするが、
国産品も高価格で現実味が薄い。
また、卸業の担当者は価格競争があるため値上げは困難だとし、
「対策を取ろうにも、為替はコントロールできない」とあきらめ顔だった。
工業用ミシン部品を手掛ける広瀬製作所(大阪市)の広瀬恭子社長は
「人手不足などもあり、日本に簡単に〝引っ越し〟はできない」と述べ、
中小企業は生産拠点を日本に移すことも容易ではないことを指摘する。
多くの中小企業にとって円安対応のハードルは高いといわざるを得ず、
先行きの不透明さが増している。
為替レートは今年後半に向かって円安が持続すると予想する。
日銀は3月にマイナス金利政策を解除し17年ぶりの利上げに踏み切ったが、
4月の金融政策決定会合では、物価や賃上げの動向をさらに見極める必要があるとして
現状維持を決定。
円を売って高金利のドルを買う取引が加速した。
今年の春闘は中小企業も歴史的な賃上げとなった。
統計に反映される夏場にかけての毎月勤労統計や、
6月に実施予定の所得税と住民税の定額減税の効果も注目される。
日銀はこれらの政策効果を見極めて金利政策の変更に向かうだろう。
令和6年4-6月期の国内総生産(GDP)速報値は8月に発表されるため、
日銀の政策変更は早くても9月の会合以降となりそうだ。
再び円安に動くかどうか、市場の関心が集まっていたアメリカの雇用統計が発表され、
市場の予想を大きく下回ったことから、円相場は1ドル=153円台から1円以上、
円高方向に振れました。
先月10日以来、およそ3週間ぶりの水準です。
雇用統計を受けて、市場ではFRBが利下げの開始時期を早めるのではとの観測が広がり、
日米の金利差の縮小を見込んだ円買いドル売りが膨らみました。
円相場をめぐっては今週月曜日に1ドル=160円台をつけたあと、
5円以上値上がりし、2日も4円以上円高に進むなど、
市場では政府・日銀が複数回、為替介入を繰り返したという見方が広がっていて、
1週間で8円を超える大幅な値動きとなりました。
アメリカの4月の雇用統計は景気の動向を敏感に反映する
「非農業部門の就業者数」が前の月に比べて17万5000人増え、
およそ24万人の増加を見込んでいた市場の予想を下回りました。
失業率は前の月から0.1ポイント悪化して3.9%でした。
市場ではアメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会が
いつ利下げを開始するかが焦点になっていて、
FRBは物価に影響する労働市場の動向を見極めながら
慎重に利下げの開始時期を判断するものとみられます。
今後の為替相場の見通しについて、
市場では為替介入が実施されたとしても
今の円安の流れを変えるのは難しいのではとの見方が広がっています。
29日、円相場は1ドル=160円を突破した後、
一転して5円以上円高に進み、
市場では政府・日銀が為替介入を行ったとの見方が広がっています。
一方、29日1ドル=154円台まで上昇した円相場は30日、
再び1ドル=157円近辺まで円安に進んでいます。
外為どっとコム総研 神田卓也調査部長
「一国の単独介入で為替相場のトレンドを変えるっていうのは
もう不可能だっていうことは、マーケットも周知しています。
これで円安が止まるという可能性は極めて低い。
特にドル円相場においては、円相場の動きよりもドルの動きが肝心になる」
外為どっとコム総研の神田卓也氏はこのように述べ、
ゴールデンウィーク中にアメリカのFOMCや雇用統計の発表など、
“ビッグイベントが目白押し”だとして、
その結果を受け”また1ドル=160円付近まであっさり
ドル高円安が進む可能性も十分ある”と話しました。
また、野村総研の木内登英氏は
「日銀がきょう発表した当座預金見通しの状況から推計した結果、
政府・日銀が5兆円規模の円買いドル売りの介入に踏み切った可能性がある」
と分析します。
ただ、あくまでも推計で、
1兆円から2兆円の誤差が出る場合があるとしています。
その上で、「アメリカの状況が変わってこないと流れは変わらない。
さらに160円超えないかというとそういうことはない。
超えると次は165の攻防になっていく可能性はある」と話しました。
一方、岡三証券の武部力也氏は
「岸田政権は景気浮揚のためにインバウンド外国人消費にも期待している。
過度な円高押し下げもできず苦渋の局面だ」と述べ、
当面は1ドル=150円から165円の間で動くのでは、との見方を示しました。
~工事について~
中津川市のお客様宅、
サッシ交換工事を紹介します。
<工事内容>
<解体工事>
既設サッシ解体・撤去
既設サッシ解体・撤去
LIXILサッシ(オーダー加工)
LIXILサッシ(オーダー加工)
サッシ取付け工事
サッシ廻り板金張り工事 ガルバリウム銅板使用
防水工事 シーリング打設
施工前



施工中






施工後


今回の契約は
西側サッシから雨水の進入があった為、
耐久性向上、断熱の向上の為、
施工に当たりました。
今後もお客様の暮らしにあった、
工事提案、施工に当たります。
最大10連休となるゴールデンウィークが始まりました。
記録的な円安となるなか、空の便は27日が出国のピークです。
記録的な円安となるなか、27日が出国のピークで羽田空港からは3万5600人が、
成田空港からは5万1000人が海外に向けて出発します。
アメリカに行く女性
「両替した時にビックリした。これだけにしかならないんだって」
「(Q.心配事は?)チップが足りるかなと」
タイに行く親子
「本当はハワイとか行ってみたかった」
中国に行く家族
「ホテルを下げるとか値段を下げるとか、外食をしないとかしかない」
「(Q.円安の影響は?)大きい。157円とか6円とかキツイ。
今から飛行機乗って行くぞーおー!」
全日空によりますと、ハワイの予約数は過去最多のおよそ1万6000人です。
ゴールデンウィーク期間中、羽田と成田からは合わせておよそ78万人が出国します。
入国のピークは来月6日です。
6月分の電気料金とガス料金は大手全社で値上がりする。
電力大手10社が発表した6月請求分の電気料金は、
5月分と比べて全社で値上がりする。
5月分から再生可能エネルギーの普及に向けて料金に上乗せされている
賦課金が増額していることに加え、
6月分は国が負担軽減策として支給している補助金が半減するため、
標準的な家庭で、東京電力では8137円から8538円に、
北海道電力では8757円から9114円となるなど、
大手10社で357円から585円の値上がり幅となる。
また、大手都市ガス4社も6月分のガス料金を発表し、
政府による負担軽減措置が半減することから、
4社全てで140円から185円値上がりする。
また、7月分の電気料金・ガス料金は、国の負担軽減策がなくなるため、
さらなる値上がりが懸念される。
日本時間24日午後9時過ぎ、
外為市場でドルが155円台へ一時上昇し、
1990年6月以来34年ぶりの高値を更新した。
上昇は瞬間的ですぐに154円台へ反落したが、
重要な節目と位置付けられていた155円台を上抜けたことで、
市場では円買い介入への警戒感が一層高まることになりそうだ。
ドルは今週に入り、154円半ばを割り込むこともほとんどなく、
歴史的な高値圏に張り付く状況が続いていた。
米国景気が想定以上に堅調で、
早ければ3月と見られていた利下げ予想が大きく後ずれしていく一方、
3月にマイナス金利の解除に踏み切った日銀の追加引き締め期待は乏しいままで
「大きく広がった日米金利差が縮小へ転じる見通しがほとんど持てない」
状況が、ドル高/円安地合いを長期化させている。
鈴木俊一財務相を筆頭に日本政府当局者は、
連日様々な表現を用いて円安のけん制を続けており、
17日に米国で初めて開催された日米韓財務相会談では、
共同声明に「外国為替市場の動向に関して引き続き緊密に協議する」と盛り込んだ。
財務相は帰国後、声明は「大きな成果」だったとして、
介入を暗示するとされる「適切な対応」につながる環境も整ったと言明した。
こうした発言を受けて、市場では介入の具体的な戦術に関する予想も出回っている。
「サプライズが必要となるため、単発の大規模介入を時間をおいて繰り返すのではなく、
より小規模かつ頻繁な介入でドル円を押し下げる手法も考えられる」という。
一方、想定以上のインフレに苦慮する米国が、
人為的なドルの押し下げ介入を容認する公算は高くないとの見方も
市場関係者の間では根強い。
26日にかけて行われる日銀金融政策決定会合で、
植田和男総裁がどのような手綱さばきを見せるのか、
市場は注目している。
~工事について~
豊川市のお客様宅、
大屋根葺き直し工事を紹介します。
<工事内容>
既設桟瓦 撤去
既設桟瓦 解体・撤去・4段積み
既設谷樋 撤去
桟瓦加工費 針穴加工
下地工事 構造用合板張り
防水工事 ゴムアスルーフィング張り
瓦桟打ち工事
屋根葺き直し工事
強力棟取付け工事
漆喰工事 シルガード使用
棟瓦葺き替え工事 七寸丸使用
施工前


施工中







施工後



今回の契約は2F小屋裏に漏水があり、
既設の瓦えを利用し外観を変えずに漏水を防止し、
土を取りの除くことで地震に対して有利に働き、
安心して暮らして頂けるように、
施工に当たりました。
今後もお客様の暮らしにあった、
工事提案、施工に当たります。
経団連の十倉雅和会長(住友化学会長)は23日、
経済のファンダメンタルズ(基礎的諸条件)を踏まえれば、
現在の円安は行き過ぎだとの考えを示した。
十倉会長は都内で開いた定例記者会見で、
過去にも政府・日銀は行き過ぎた円安には介入した経緯があるとし、
口先介入か実弾で行うかも含めて「適切に判断されると思う」と語った。
一方で、日米の金利差などさまざまな情報を踏まえて投機的な動きになっている側面もあり、
「短期で見て、どうやったら解決できるかというのはなかなか出てこない」
とした上で、中長期的には購買力平価を反映した水準に収束するのではないかとも述べた。
米連邦準備制度理事会(FRB)による早期の利上げ観測が後退する中、
為替市場では日米金利差を意識した円安の流れが続いており、
23日には一時1ドル154円85銭と約34年ぶりの安値を付けた。
円安は輸出企業の業績を押し上げる一方、
原材料などを輸入する内需型企業のコスト上昇要因となることから
財界からは過度な円安に対する懸念の声が上がっている。
特に中小企業では原材料価格や人件費などのコスト上昇分の価格転嫁が
十分に進んでおらず、
物価高と円安のダブルパンチで倒産に追い込まれる企業も少なくない。
中小企業が多く加盟する日本商工会議所の小林健会頭は今月開いた会見で、
円安に対する懸念を示し、他国との協調介入を含めて考えてもらいたいと発言した。
日本政府などによるけん制の動きも活発化しており、
市場では介入に対する警戒感が高まっている。
主要7カ国(G7)は17日に開いた財務相・中央銀行総裁会議で、
為替の過度な変動は経済に悪影響を与えるとしたコミットメントを
共同声明で再確認した。
また、日米韓の財務相の共同声明には、急速な円安とウォン安に関する
懸念を認識するなどとする文言が盛り込まれた。
鈴木俊一財務相は23日午前の参院財政金融委員会で、
米ワシントンで開かれた一連の会議で為替の急激な変動を懸念する考えを
確認したことから、介入を念頭に「適切な対応につながる環境が整った」との認識を示した。
政府は22日、200ある国の基金事業を点検した結果、
使う見込みのない資金が積み上がっているとして5466億円を
国庫に返納させると発表した。
数年分の資金をまとめて予算計上する基金は、
チェックの甘さから無駄な支出につながりやすい。
政府は基金を伴うすべての事業に成果目標を定めさせ、ルールを厳格化する。
同日のデジタル行財政改革会議で、
国の基金事業すべての点検結果を河野太郎行政改革担当相が報告した。
2023年3月末時点で、国の基金は計16・6兆円の残高がある。
点検結果によると、事業自体が終わった後も基金を運営・管理する
独立行政法人や公益法人などの事務所費や人件費など
管理費の支出が続いているケースがあり、
こうした11事業を24年度末までに廃止する。
このほか4事業を既に廃止した。
15の廃止事業に加え、今後も存続する約40の事業についても、
23年度分の約4342億円、24年度分約1124億円は使う見込みがない資金と判断。
計5466億円を国庫に返納させる。
国の予算編成は年度ごとに国会の審議を経て決めるのが原則で、
複数年度分の予算を一挙に計上する基金は事前に必要な額を
見込むことが困難な場合などに限って認められる例外的な措置と位置づけられている。
ところが、近年は経済対策の規模を大きくしたり、
コロナ禍に対応したりするためだとして基金新設や積立の増額が顕著になっている。
基金はいったん設立すると所管する省庁や独立行政法人の裁量に任され、
国会による監視の目も届きにくくなるため批判が高まっていた。
こうした批判を受け、政府は基金設立のルールを見直し、
すべての基金事業について定量的な目標を設定した。
基金への予算措置は3年分程度までとし、
その後も予算をつけるかは事業の目標の達成具合を見て判断する。
また、基金事業は原則として10年以内に終了させる。
現時点で10年を超えている事業は、今後3年以内に終わらせることにする。
また、経済産業省では基金事業に関わる補助金交付基準の策定や
審査を民間に任せていた事例が多くあった。
公平性の観点から問題があるため、民間への外注を事実上禁止するよう
ルールを見直した。
新ルールでは、国と基金を運営・管理する独立行政法人などが交付基準を策定し、
国が承認する仕組みにする。
人口減少問題への関心を高めるため、民間組織「人口戦略会議」がまとめた
報告書の概要が19日判明した。
2020~50年の30年間で、子どもを産む中心の年代となる
20~39歳の女性が半数以下となる自治体は「消滅可能性」があるとした上で、
全体の40%超の744自治体が該当すると分析している。
24日に公表予定で、自治体に地域の実情に応じた対策の充実を呼びかける。
人口減少を巡っては、別の民間組織「日本創成会議」が14年に報告書を公表した。
国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の地域別将来推計人口を基に
独自にデータ処理した結果、896自治体は10~40年に20~39歳の女性が半数以下となり、
消滅の可能性があるとした。896自治体のリストも公表した。
10年ぶりの今回は、独自のデータ処理をせず最新の社人研推計をそのまま当てはめた。
見かけ上は、該当自治体数は10年で150程度の減少となった格好だ。
人口戦略会議は外国人住民の増加が要因で、少子化自体には歯止めがかかっていないとみている。